「沓」という言葉、土木技術者ならご存知の方も多いと思います。
でも、日常生活ではあまり使わない漢字ですよね。
常用漢字でもありませんし普段使われないので、土木技術者や、橋梁に関わる人以外にはあまりなじみがありません。
ひょっとすると、最近使われることも減ってきているので、今の若い技術者で知らない人も多いかもしれませんね。
今回はこの「沓」について、説明していきたいと思います。
「沓」の読み方
沓という漢字、橋梁の世界では「しゅう」と呼んでいます。
一昔前には一般的に用いられていた言葉で、図面で目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
でも、PCで単純に「しゅう」と打ってこの漢字が出てきますか?
ほとんどの場合、出てこないと思います。
実はこの「沓」という漢字を「しゅう」と読むのは非常に特殊な読み方で、普通は「とう」「くつ」などと読みます。
「雑沓(ざっとう)」(=「雑踏」)などと使われるようですね。
私は普段使わないPC等、「沓=しゅう」が通用しない場合は、「くつ」と打って変換しています。
なお、沓は常用漢字ではなく、人名などにしか普通使われないそうです。
では、なぜ「しゅう」と呼ぶのでしょうか?
これは、そもそも「くつ」と言う意味のある「沓」と言う漢字を、「くつ」→「shoe」→「シュー」と呼ぶようになったからだと言われています。
どういう意味?
では、沓の意味とは何なのでしょうか?
調べてみると、どうやら土木の世界で使われる場合と、一般的に使われる場合とではちょっとイメージが変わってくることが分かりました。
2つの場合に分けて沓の意味について説明していきます。
土木の世界では?
沓(しゅう)とは、一般的に「橋台に橋桁を載せる為に取り付けた部材」=支承のことを言います。
現在は「支承」と呼ばれることが多いのですし、いろんな書籍で「支承」という語がつかわれていますが、今でも通称として「沓」と呼ぶ場合もあります。
また、その名残で、支承の一部を指す場合にも「上沓」「下沓」「沓座」などと言った言葉が残っていますね。
沓と支承の違いは?と聞かれることがたまにあるのですが、沓と支承の違いは特にないと考えて間違いないでしょう。
ただ、正式な文書や技術系基準では「支承」と呼ぶのが正解ということは頭に入れておいた方がいいかもしれません。
一般的には・・・?
漢字辞典で調べると、沓にはいろんな意味があるようです。
例えば以下の通り。
なめらかにしゃべる
漢字辞典HP< https://kanjitisiki.com/zinmei/287.html>より
かさなる。こみあう。
むさぼる。
くつ。はきもの
あまりぴたりと会うものはありませんが、土木用語で使われている場合は4個目の意味が基になっていると考えられます。
「踏む」という漢字の一部にもなっているように、元々「靴(くつ)」と同じように、重なっているものの下にあるものや、踏まれているものを指すようです。
また、漢字の成り立ちは、漢字上部の「水」と下部の「曰」を合わせて、「水の流れのようにすらすら言う」ことも示しているようです。ちなみに、下の「曰」は「日」(にち、ひ)ではなく、「曰」(いわく)が基になっています。
なんでなめらかにしゃべることと「くつ」が同じ漢字で表されるのでしょうね~?
沓の付く言葉
沓座(しゅうざ)
下部工と支承との間にある支承が乗る部材。
沓座は、下部工の出来高(構造高)を現場にて調整したり、下部工のうち上部工が乗る部分の補強の目的で設けられる場合が多いです。
沓座には、調整モルタル(RC下部工)・調整プレート(鋼製下部工)などが用いられるのが一般的ですね。
上沓、下沓(うわしゅう、したしゅう)
支承の上部構造と下部構造のこと。
読み方はうわしゅう(うえしゅう)やしたしゅうなどと言われます。
支承の詳細構造について設計すると、それぞれ上部と下部でこのような言葉が使われる場合があります。
支承の種類も様々なので、上沓、下沓と呼べるような部分の無い支承も多くあります。従来から用いられてきた鋼製の支承では上沓、下沓がはっきりしている場合が多いです。

沓摺(くつずり)
この言葉は建築の分野で使われているそうです。
ドア枠の下部、下枠に当たる箇所を指します。
沓摺りと敷居の違いが分かりにくいらしいのですが、2者の違いは、沓摺りがドア(片開き戸)の下枠なのに対し、 敷居は引違い戸や片引き戸など、レールや溝が付いた引き戸の下枠であるということです。
まとめ
日常生活では使われない「沓」という言葉。
今も土木業界では多く使われる言葉なので、何を意味するかはしっかり理解しておきましょう!
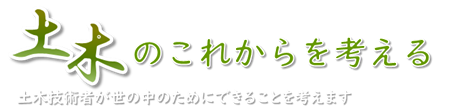


コメント
ありがとうございます。初めて知りました。
何か意味がわからず、困っておりました。
ご覧いただきありがとうございました。
なかなか普段使わない漢字ですので、わかりにくいですよね。
今回はお役に立てたようでよかったです。
何かございましたらまたコメントください。
今後ともよろしくお願いします。